制震と断熱の住宅建設
住宅勉強会で絶対的な人気講座が、この「住宅計画セミナー」です。
住まいづくりを計画される多くの方は、どういう順序で計画を進めて良いかが判りません。計画に要する準備期間をどれ位取るのか?
何をどういう順番で進めるのか?
どうしたら失敗しないのか?
そんな疑問を多くの方が持たれているのです。
家づくり計画は、一生に一度の大事業です。絶対に後悔したくはありません。
にも関わらず、建築白書の調べでは、新築された方々のアンケートで82%の人が「住まいづくりで失敗して後悔している」と答えています。
私共では、多くの方からご好評頂いているこの住宅計画セミナーをどなたでも受講出来るように準備させて頂きました。
ぜひ、この機会に正しい住宅知識を習得されてみては如何でしょうか。
本セミナーであなたが得られる知識の一部をご紹介すると・・・
 |
家づくりに後悔する人は、ここに原因がある!何故、後悔する?・・・それは・・・ |
 |
住まいづくりのトラブル続出!・・・オーダーメイドで100点を取る方法とは・・・ |
 |
相見積のメリット、デメリット・・・際限なく追加工事が増える理由とは・・・ |
 |
欠陥住宅が出来てしまう原因とは・・・ |
 |
悪質な業者から守ってくれる法律とは?契約書サインの前の注意事項とは・・・ |
など、など。
とても、貴重な情報になることは間違いないでしょう。
ぜひ、この機会に本セミナーを受講されて、正しい知識を入手されて失敗しない注文住宅建築計画をお進めください。
制震と断熱の住宅建設
多くの方が、そう思われるは当たり前です。
しかも一住宅会社が・・・おたくの会社は何様のつもりか?
そういう声が聞こえてきそうです。
私もそう思います。
自分の意見だけでそうしたことを述べるのであれば、尚更でしょう。
そもそもどういう住宅会社が良い業者なのか?などを定義した書籍も今まではありませんでした。あっても、明確な根拠もなく、その理由が、同じ団体に所属している程度です。
私から言わせれば、そもそも、その時点で話がおかしいのです。
生活者は、根拠のある正しい情報を望んでいるに関わらず、情報提供する側は、しっかりとした根拠もなく、同じ団体を、ただ、同じ志を持っている、という程度で良い業者と判断しているからです。
私は、あとで後悔しない「いい家」の建て方!(業者選びですべては決まる)という書籍をあの大手教育書籍発行元の学研さんから出版しました。この書籍は、新宿紀伊国屋本店の建築・土木部門にて3週連続の売上ランキング1位を確保し、その後も順調に売り上げを伸ばし、順調に売れているようです。
それは、何を意味するかと言うと、その内容に共感する多くの人が居て、支持され続けている、ということです。
私は、インターネットの顧客満足評価の高い住宅&リフォーム会社の代表と3年という長い年月を掛けて、優良会社の確かな基準づくりをお手伝いしてきました。
そして、その後、全国の業者さんにセミナー活動を行ったり、優良会社の視察を行ったりして自らの調査も行いながら、片方では、優良会社の認定審査員も行ってきており、現在も毎月1回のペースでその審査を行っております。
そうした活きた経験があるからこそ、第3者的に見てきたからこそ、他にない圧倒的な優位的な情報であると言い切れるのです。
本セミナーを受講されて得られる知識の一部をご紹介すると・・・
 |
家づくり計画の決め手!優良会社の選択基準とは? |
 |
正しい選択基準!ここをこうして見る!ここをチェックする! |
 |
優良会社にある顧客満足度のしくみとは? |
 |
何が違う?優良会社とそうでない会社との違いとは? |
 |
ここを間違えるとすべてが狂う住宅計画! |
など、など。
とても、貴重な情報になることは間違いないでしょう。
ぜひ、この機会に本セミナーを受講されて、正しい知識を入手されて失敗しない注文住宅建築計画をお進めください。
制震と断熱の住宅建設
東日本大震災でオール電化住宅への信頼度は、一気に下降しました。環境負荷の少ない家を建てることは、これからの課題と言えます。
ガス併用住宅のメリット・デメリットはご存じですか?
オール電化住宅のメリット・デメリットはご存じですか?
あなたのライフスタイルによって、どちらが適しているかが、変わります。どちらが良いかは、しっかりとこれからの住まい方によって変動するのです。
しかし、多くの会社は、オール電化を推奨する、という程度が今までの提案でした。そこに住まう方のライフスタイルをしっかりと理解しなければ、どちらが良いか、判断できないないに関わらず、です。
私共では、これからの気になる電気料金や太陽光発電との併用、緊急時はどうか?など、様々な角度からの基本的なお話をさせて頂きます。
更にご希望の方には、東京ガスさんと東京電力さんのご協力を得て、実際の体感ツアーも実施しております。そのツアーには、専用アテンドも付けてご案内頂く、私共だけの特別企画でもあります。
まずは、本セミナーを受講されて、今の最新エネルギー事情と設備をご確認されると役立つと思われます。
エネルギーを選択するという行為をひとつ間違えると、一生涯に渡り、損し続けることになります。そうならない為にも、本セミナーをご活用頂き、損のない住宅計画をお進めください。
本セミナーを受講されて得られる知識の一部をご紹介すると・・・
 |
オール電化住宅とは何なの?ガス発電住宅とは何なの?そのメリット、デメリットが判る! |
 |
初期コストは?ライニングコストは? 今の光熱費と比べると、どうなるの? |
 |
緊急時は、どうなの?電気が良いの?ガス併用が良いの? |
 |
電気料金体系はこれからどうなるの?太陽光発電との併用はどうなの? |
など、など。
とても、貴重な情報になることは間違いないでしょう。
ぜひ、この機会に本セミナーを受講されて、正しい知識を入手されて失敗しない注文住宅建築計画をお進めください。
予約制となりますので、ご希望の候補日を3候補日程、ご記入の上、光熱費削減セミナー受講希望とお知らせください。





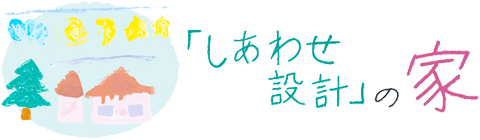
 ご相談
ご相談