制震と断熱の住宅建設
みなさんは、いい家を建てたいと考えている、と思います。多くの方は、建てた後に見える部分に拘ります。キッチンの仕様、お風呂の仕様、などなど。
売る側もそれを理解しており、仕上がって良く見える部分にコストを投じております。勿論、そうしたことは重要です。
しかし、仕上がって見えなくなる部分はもっと重要です。
現実的には、仕上がって見えなくなる所のコストを落とす会社は存在しますし、そうした会社に頼んで欲しくはありません。
しかし・・・・・どういう所を見たら良いか判らない!!
というのが本音ではないでしょうか?
そうです。それを、しっかりとご説明する機会をご提供させて頂きます。その基準を知ることで、本当に家で大切な所を理解することが出来ます。そして、ぜひ、そうした知識をこれからの住宅計画にお役立て頂ければ嬉しい限りです。
実際に建てている建築途中の物件をご案内させて頂きます。本予約見学会で、あなたが得られる知識の一部をご紹介すると・・・
 |
構造部分は、何処をチェックするかが判る!! |
 |
建てていい家、建ててはいけない家の基準が判る!! |
 |
現場のチェックポイント、どういう業者選びをすれば良いかが判る! |
 |
しっかりとした家を建てられるようになる! |
 |
抜き打ち見学の手法が判る!出来るようになる! |
など、など。
とても、貴重な情報になることは間違いないでしょう。
ぜひ、この機会に本見学会を受講されて、正しい知識を入手されて失敗しない注文住宅建築計画をお進めください。
予約制となりますので、予約構造見学会希望とお知らせください。日程調整をさせて頂き、改めましてご連絡させて頂きます。
制震と断熱の住宅建設
家づくり計画で最も大切なことって何だかご存じですか?それは、実際に建てられた家が、全部でいくら掛かったかを知ることです。
住宅展示場は、膨大なコストを掛けて建てられていることを考えると部分的な参考にはなりますが、決して、等身大の家とは言えません。
そうした場合、自分たちの身の丈にあった家、自分たちの予算に見合った家を見ることです。そして、その予算内で建てられる家を建てることが重要です。
私共では、多くのお客様のしあわせな家づくりのお手伝いをさせて頂いており、多くの物件が実際の工事を行っております。その中で、現在、ご案内出来る実際の家をご案内させて頂きます。
本予約完成見学会に参加されて得られる知識の一部をご紹介すると・・・
 |
その建物が実際にいくら掛かったのかが判る! |
 |
実際の家なので、大きさ、空間の把握が出来る! |
 |
空間を有効利用する設計のポイントが判る! |
 |
採光、風通し、立地状況に応じた快適な家づくりのポイントが判る! |
など、など。
とても、貴重な情報になることは間違いないでしょう。
ぜひ、この機会に本予約完成見学会を体感されて、正しい知識を入手されて失敗しない注文住宅建築計画をお進めください。
予約制となりますので、予約完成見学会希望とお知らせください。
日程調整をさせて頂き、改めましてご連絡させて頂きます。
制震と断熱の住宅建設
良い土地って、どう見抜くかご存知ですか?
多くの方は、その真実を知りません。私共の会社にも多くの土地を探されてお客様からお問合せを頂きます。
しかし、土地は買ったけれど、予算がキューキューで家に回せるお金がほんの〇〇〇万円しかない、という問い合わせがとても多いのです。
これは、何を意味するか、というと想定以上に土地に予算を奪われ、建物の資金がなくなってしまう典型的な失敗例のひとつです。
「土地の上に住むのか?建物の上に住むのか?」良く判らない状況になってしまっているのです。
そんなお客様が圧倒的に多いのが、今の実情なのですが、残念ながら、これから土地を購入される方は、そうした情報は一切知りません。
しかし、何故、そんなことが起きてしまうのか?
それは、事前の情報不足が大きな原因と言えます。
もっと、正しい情報を入手していれば、そんなことにはならなかったはずです。
そこで、私共では、土地探しのプロが、実際の土地を一緒に車で回り、買っていい土地、そうでない土地を建築士の視点からアドバイスさせて頂きます。これを知ることで、大きなアドバンテージになることは間違いありません。
本ツアーに参加されて得られる知識の一部をご紹介すると・・・
 |
お得な土地の価値観が判る! |
 |
後から追加・追加と、計上される様な土地が判る! |
 |
建築士の視点と不動産業者の視点の違いがはっきり判る! |
 |
失敗しない土地探しが出来るようになる! |
 |
お買い得、そうでない土地の差が判るようになる! |
など、など。
とても、貴重な情報になることは間違いないでしょう。
ぜひ、この機会に本ツアーを体感されて、正しい知識を入手されて
失敗しない注文住宅建築計画をお進めください。
予約制となりますので、土地ツアー参加希望とお知らせください。
日程調整をさせて頂き、改めましてご連絡させて頂きます。





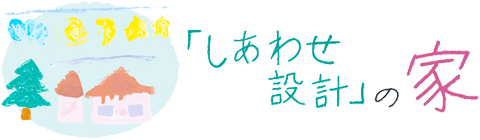
 ご相談
ご相談